-
 Dolive 対談 / インタビュー
Dolive 対談 / インタビュー戦略と徹底力で実現。2年で棟数を倍増させた成長の軌跡
-
 対談 / インタビュー 住宅業界TOPICS
対談 / インタビュー 住宅業界TOPICS“暮らし方提案”と魅力的なプロダクトで、住宅業界の認識を塗り替える。|新建新聞社 三浦氏×CEO 林 対談
# Sunny Track House# LIFE LABEL -
 LIFE LABEL 対談 / インタビュー
LIFE LABEL 対談 / インタビューLIFE LABELとHAPPY OUTSIDE BEAMSが作る家!キーワードは“外遊び”を楽しむ拠点
# 住宅デザイン# Sunny Track House# LIFE LABEL -
 住宅市場
住宅市場潜在欲求を可視化!ギア好きのための家「THE HOUSE GARAGE PROJECT」が拓いた新たな市場とは
# 住宅デザイン# Dolive -
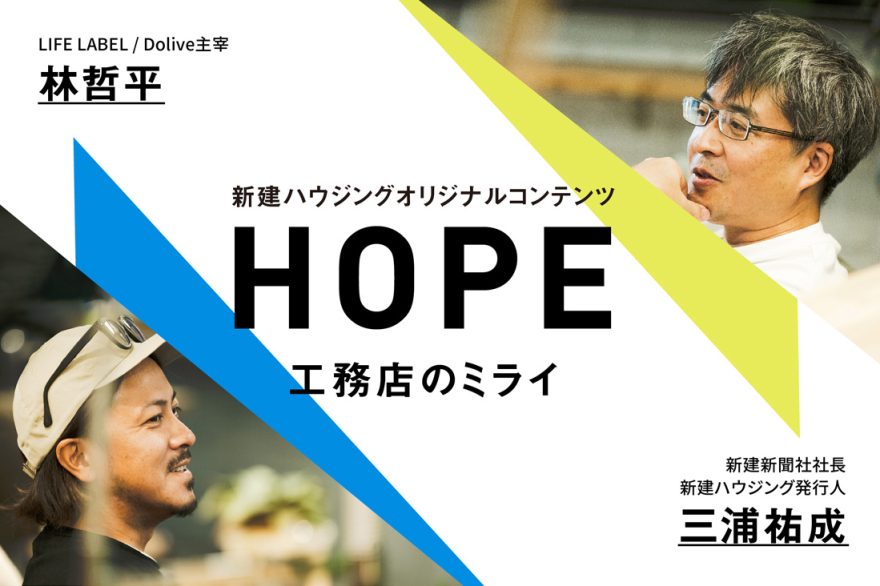 対談 / インタビュー 住宅業界TOPICS
対談 / インタビュー 住宅業界TOPICS工務店・住宅業界の未来を語る『HOPEー工務店のミライ』|新建新聞社発行人 三浦氏×CEO 林による対談レポート
「泊まりたくなるデザインの勝ち筋とは」|リフォーム産業フェア2025対談レポート

INDEX
introduction
2025年9月17/18日に開催されたリフォーム産業新聞社主催「リフォーム産業フェア2025」。このイベントで開催されたセミナーにLIFE LABEL・Dolive主宰の林が登壇しました。
テーマは「住宅業界はもっとデザインにこだわるべき。泊まりたくなるデザインの勝ち筋とは」。一緒に登壇したのは、Doliveの「NIHON NOIE PROJECT」なども共に手掛けた建築家・谷尻誠氏と、「地材地建」をキーワードに林業から製材所・設計事務所・工務店業までを手掛ける石田伸一氏。また施工管理アプリ「ダンドリワーク」を運営する加賀爪宏介氏がファシリテーターを務めました。
住宅業界にとってデザインとはなんなのか、AIが登場したことで住宅デザインはどうなるのか、デザインの感性を磨くにはどうすればいいのか……などさまざまな切り口で語り合いました。
そもそもなぜ住宅にデザインは必要なのか?

加賀爪:本日聞き手を務める加賀爪です。よろしくお願いします。まず今回のセミナーのタイトルにもありますが、そもそも住宅にデザインってなぜ必要なんでしょうか?
石田:僕は「デザイン」というものを、問題を提起するところから始めて解決まですることだと捉えています。言い換えれば、思いを込める営みとも言えるでしょう。そもそも世の中のあらゆるものは、誰かがデザインしたからこそ存在しているわけで。その思いを受け継ぐためにも住宅業界はデザインに注力しないといけないなと思っています。

加賀爪:完璧な答えですね(笑)。谷尻さんは、いかがでしょう?
谷尻:正直なところ僕は、住宅デザインって本当はやらなくていいんじゃないかと思ってるんですよ。今、対談が行われているこの部屋だって、そこまでデザインされていないじゃないですか。ここで対談が行われているから今は「イベントスペース」になっているけれど、ここでご飯を食べれば「レストラン」になるだろうし、アーティストが作品を飾ったら「ギャラリー」にもなるでしょう。どんな使い方でも、それぞれの機能をちゃんと担保できると思うんです。
ただ、どうせ空間をつくるなら選ばれたいじゃないですか。僕の口癖は「比較優位性」。ほかと比べられても選ばれる理由をどうつくれるか。住宅デザインはその一つの手段でしかないと思っています。
加賀爪:最初からデザインで勝負しようとは思っていないんですね。
谷尻:デザインがいくら良くても、最終的には好き嫌いで選ばれるわけですからね。だから選ばれる確率を上げるには、デザイン以前のところからデザインしないといけない。その意識が希薄な気がするんですよね。

林:僕が運営しているLIFE LABELやDoliveは、カルチャーを起点にデザインへと落とし込むことが多いんです。人って、生まれてきてからどんなエンタメに触れてきたかによって感性が形づくられるじゃないですか。「あの映画に出てくるような空間に暮らしたい」みたいな漠然としたイメージって頭の中にあると思うんです。それを忠実にデザインで再現できるかどうかは考えていますね。
ただ一方で、デザイン性って、現場の職人さんの手によって左右される側面もありますよね。建築家の方がつくるような一点ものの住宅なら尖ったデザインも再現しやすいかもしれないけれど、市場に流通させる住宅商品だとそうはいかない。そこは難しいなと思いますね。

加賀爪:ちなみに谷尻さんは建築家として、イメージするデザインをかたちにするために現場をどう捉えているんですか?
谷尻:「現場のことをしっかり考えた上で、あえてその場では考えない」といったイメージですかね。現場で言いにくいことを言わなければ職人さんからは怒られないし、自分も嫌われない。でも、いいものはできない。あえて気を遣いすぎないことは、意識しているかもしれません。
「お客様からお金を預かってクオリティの高い住宅を納める」という役割がある以上、嫌われようが何を言われようが、「絶対にこういう家を作るんだ」という議論を重ねていいものをかたちにする。それがプロだと思っています。
加賀爪:そうすると、結果的に完成したときに職人さんも喜びそうですよね。

谷尻:そうなんです。何のためにやるかというと、その人のためじゃなくて、もっと先にある「みんなが良かったね」と言えるその時間のためにエネルギーを使っているわけです。
石田:行き着く先は「オールウィン」なんですよね。僕も、施主さん、設計する人、施工する人、素材となる木を植えた人……関わる方々全員に対しての最適解を見つけようとしています。
来るAI時代。住宅業界のデザインはどうなる?

加賀爪:次は昨今業界を賑わせている「AI」について話を聞きたいと思います。たとえば、谷尻さんが手掛けた建築デザインを大量にAIに読み込ませれば、「谷尻誠」風の住宅デザインができるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょう。
谷尻:実際に僕が立ち上げた「Mietell」というサービスでは、僕が手掛けてきた建築デザインをAIにガンガン読み込ませてデザインを生成しています。そこで僕がやっていることといえば、AIが取り込むデータベースとなること。AIはすでにできあがっているものを集めて、解析して、作り出すことはできるけど、その根源となる「種」まではつくれない。だから、種がつくれる人が生き残って、種がつくれない人間はAIに淘汰されてしまうんじゃないでしょうか。

石田:その種が発芽して、どんどん増えたり、大きくなったりしていくんでしょうね。AIがその種をブラッシュアップして別の種をつくるかもしれないし、人間からまた新しい種が生まれるかもしれない。でも、いずれにせよ根源となっているのは「谷尻誠」という人間であることは変わりません。

加賀爪:ただ、まだ住宅業界では取り込んでいるデータの数も限られていると思うんですけど、何十万とデータが増えていくとブレイクスルーするらしいですね。たとえば囲碁や将棋の世界では、AIが竜王に勝った世界線が登場しています。その点については、どのように考えていますか?
石田:でも、今のところAIはプロンプトと既存のデータから生成するだけなので、前例のない新しい発想は難しいと思うんです。香り、景色、音、肌触り……五感で感じたものからクリエイティブに発想するのは人間がするべきことかなと。

谷尻:そもそも「情報」って感動しないんですよね。以前、メキシコの名建築家ルイス・バラガンの邸宅を見に行ったとき、ツアーガイドが「次の部屋はこういう部屋になっております」と説明するんです。それが予定調和すぎて全然感動しなくて。でも別の部屋に行ったとき「どうぞ勝手に見てください」と言われて、あちこち自由に入って見たら感動で鳥肌が立ったことがありました。
林:捉え方によっては、AIって「人として何が大切なことなのか」って問い直してくれる存在だと思うんです。「人と人が関わりながら動くのっていいよね」「コミュニティのつながりって大事だよね」ということに気づかせてもらえる。

石田:情報過多の時代だからこそ、思い、感情、情熱……そういった部分が人間が担うものなのかなと。感動する建築を作ることが大切だと思います。
谷尻:「知識より創造性が大事」だと、あのアインシュタインも言っていますからね(笑)。

デザインの感性を磨く前に必要なことがある
加賀爪:続いての問いに行きましょう。みなさんはデザインの感性を磨く前に必要なことって何だと思いますか?
石田:もともと僕は感性やセンスって先天的なものだと思っていたんです。でも、願望を込めて言うと、磨けるものでもあると思っていて。そこに必要なのは、体験・体感すること。ネットや雑誌で情報を取り入れてわかった気になるよりも、事前情報を持たずに足を運び、その場の空気を感じることが大切だと思うんです。そこで鳥肌が立つ経験ができるといいのではないかと思います。

谷尻:たしかに海外の豊かな文化の中で育った人は、センスがもともと身についている場合がある。そんな環境にいない私たちでも、後から磨くことはできますよね。ただし、いちいち問い直し、いちいち考えないとダメ。
たとえば、今時みんなiPhoneを手にして、みんななんとなくいい写真が撮れるようになって、みんな同じような写真がInstagramに上がっているわけじゃないですか。それでセンスが良くなるわけがない。
本当にセンスを良くしたいなら撮り方を考えないといけませんよね。「みんなが同じものを持っているなら、みんなと違うやり方はないのか。どうやったらもっと良い写真なるのか」そうした問いを自ら立てられないと、センスは良くなりませんよね。
加賀爪:素敵な写真がInstagramに上がっていると、「この住宅会社に頼みたい」という集客にもつながりそうですよね。

谷尻:いい写真を撮っていると「この会社は、きっとそういう感覚を持っているはずだから安心して頼める」と思ってもらえる。もっと言えば、写真だけじゃありません。発する言葉や文章、普段見ている世界や取っている行動……全てが信頼感につながっていく。「そういう発信は自分は苦手かもしれない」と思うなら、それをどうやって克服するか、どうやって相手に伝えるか。それもデザインなんです。
そういった努力を丁寧に重ねていくとセンスが良くなるし、お客様からの信頼感も構築されて、自ずと仕事が集まってくるはず。
林:住宅デザインって結局、「フォルム」と「テクスチャー」で構成されていると思うんです。しかも、ほとんどがテクスチャーを変えれば何とかなることが多い。家に帰りたくなるかどうか、外から見て「あれがうちの家なんだ」と胸を張れるかどうかが重要なのに、そうじゃない家が多すぎる。外壁材メーカーさん、一緒に頑張りましょうと伝えたいですね(笑)。

林:また、僕は映画業界出身なんですが、「カメラワーク」と「ディテール」の関係と言ってもいい。岩井俊二監督のような雰囲気とか、『カメラを止めるな!』のようなワンカットでの撮影とか。「何をどう切り取って表現するか」といった視点は、映像やグラフィックから大いに学ぶことがあると思うんです。
谷尻:違うジャンルのものに触れたときに「それだ!」と気づけるのがまさにセンスだと思います。日頃から、アンテナを張って物事を見ているかどうかが重要ですよね。

まとめ
加賀爪:最後にみなさんに伝えたいメッセージをお一人ずつお願いします。
石田:自分が建てた住宅は、自分が死んでからも残ります。それを自分の子供に自慢できるかどうか。建築の仕事は街並みや風景を作る仕事だからこそ、しっかり考えて、やりきって、後世に残していくという視点が重要だと思います。
谷尻:お客様の言うことをそのまま鵜呑みにしてつくってはいけません。たとえば「明るいフローリングがいい」と言われても、「なぜ明るいフローリングを求めるのか」「暗いフローリングにすることで、どんなネガティブな要素とポジティブな要素があるのか」をちゃんと提示して選んでもらう必要がある。
遠回りかもしれないけれど、そうしたスタンスでデザインを世の中に提示していくのが我々の仕事です。
林:私たちがやらなければいけないのは、会社やサービス、ブランドが持っている人格=「ブランドパーソナリティ」を作ることです。Doliveを例にすれば、世の中を斜めから見つつ、「もっとポジティブに楽しもうぜ」と言っていそうな人格があります。自社のブランドパーソナリティを形成し、その会社がどうしたいのか、そのブランドがどうあるべきかを考えていく──その視点をぜひ持ち帰っていただければと思います。

この記事に関するサービス
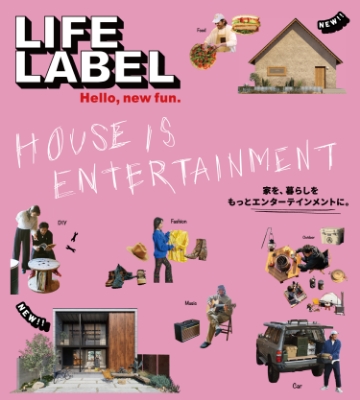
LIFE LABEL
好きなLIFE STYLEから自分にあったお家が見つかる。
LIFE LABELマガジンで自分好みの暮らしのサンプルを探して、そんなライフスタイルにぴったりなLIFE LABELのお家を見つける。
ユーザーにとって最適な家探し体験ができるお店です。

Dolive
家づくりのアイデアが生まれるプラットフォーム。
家づくりのアイデアが集まる情報Doliveメディアや、自分たちが暮らしたい家を想像できるシミュレーションアプリを軸に、オリジナル住宅「Dolive HOUSE PJ」や「HOUSE RECIPE」も展開。

